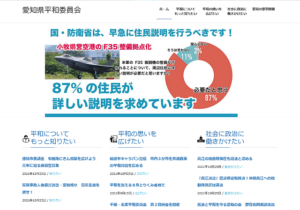安保法制違憲訴訟 平和の問題は憲法と切り離してはならない

今年で強行採決から10年を迎える「安保法制」の違憲判断を求めてたたかわれている「安保法制違憲訴訟」控訴審の第3回口頭弁論が、1月21日、名古屋高裁で開かれました。今回は、平松清志、川口創両弁護士が「控訴準備書面4・5」の要旨を弁論、控訴人である井戸孝彦さんが意見陳述を行っています。
「閣議決定による憲法解釈の変更という手法で集団的自衛権の行使を認めたもので……まさに、解釈によるクーデター」――「準備書面4」では、その内容と制定手続きの違憲性を追及しました。わが国が攻撃を加えられていなくても同盟国の紛争に武力行使を行うことは、9条2項の「交戦力」の行使にあたること、元内閣法制局長官が「政府も国民も、憲法9条の下では集団的自衛権を行使できないことを実践してきた」と証人喚問で答えていることをあげて、「政府の政策判断には……憲法の制約を免れることはできない」と断じるのです。
「準備書面5」は、憲法9条をないがしろに進められる軍事体制の現状を告発します。見捨てられの恐怖と巻き込まれの危険の「同盟のジレンマ」に対して、憲法9条こそが防波堤であり、その「安心供与」機能には大きいものがあると訴えるのです。控訴人として意見陳述を行った井戸さんは、「安保法制」への不安を語り、「権力に忖度せず、司法権を行使して憲法判断を」と求めました。
閉廷後に場所を移して行われた報告集会では、準備書面を用
意し弁論した弁護団の発言が相次ぎました。安保法制後拍車のかかる軍拡に、「愛知の軍事産業の今を見ていると、自分自身が加害者になっていると感じる。軍事体制は、自衛隊だけではなく私たち自身の生活が組み込まれている」「軍事費に使われているのは私たちの税金であることを忘れてはならない」の発言が、この訴訟の重要性を訴えています。控訴審はこの先、証人喚問の準備を進めながら、4月15日に次回第4回口頭弁論を開きます。